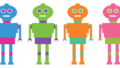こんにちは、まんぷくケアプランのまんぷくです(●´ω`●)
先日、別の法人に務めているケアマネになって1年の後輩に
「上司に”ご利用者の相談窓口は一つにするように”と指導を受けたのですが、いまいちピンとこないんですよね」
と相談を受けて、その時に実際に伝えた内容をつぶやいていきたいと思います(●´ω`●)
🏠なぜ窓口は一つの方が良いのか
結論は上司の言う通りです。窓口は一つの方が良い。
※ここでいう窓口というのは、実際に普段ケアマネやサービス事業所と連絡を取り合う代表者の事ですね。緊急時に繋がらなかったときにいくつか連絡先の候補を知っておくのは別です。
〇窓口が一つの方が良い理由は
- 事業所が連絡を取りやすくスムーズ
- 家族の意向を一本化しやすい
- 結果的に家族間で話し合う習慣ができる
逆に、複数の窓口だと
- 情報伝達に時間がかかる
- 意見の食い違いで話が進まない
- “誰が決めるのか”があいまいになる
大切なのは、“誰が情報のハブになるか”を決めておくこと。
関係者が多いほど情報は豊かになりますが、整理して伝える役割がいないと混乱します。
ケアマネの中には「家族全員(10名ほど)に連絡しろ!」と怒鳴られたことがある人もいるそうです。これは極端な例ですが実際の話です。
💬「普段から意向を話しておく」の大切さ
「窓口=代表者」を決めることは、単に連絡先を一本化することではなく、家族が事前に方向性を話し合うことにつながります。
お風呂に入れなくなったらどうするか
トイレの失敗をするようになったらどうするか
どのラインまできたら施設を検討するか
あるいは家族が同居するか
あくまで一例ですが、こういったことなどを家族間で話をしておく。
そして代表者がケアマネにも伝え、これから先の動きを具体的に決めておく。
そうすればいざというときにドタバタすることもなく、おちついてその時の状況に応じて代表者が決定していくことができます。
ちょっとだけ耳の痛いお話になるかもしれませんが、
考え方としても、ケアマネやサービス事業所はあくまで
「ご本人やご家族の意向を尊重してサービス提供をする」人たちです。
なので、ご本人やご家族があくまで主体で考え、動いていくことが必要です。
⏰時間との勝負になることも
介護の現場では、「今日中に決めないと受け入れできない」といったケースもあります。
その時に「家族会議をしてから…」では間に合わない。
だからこそ、日頃から代表者を決めておくことが大切なんです。
例えば緊急でショートステイが必要であったりした場合、ショートステイ側が
「本日中にお返事を頂ければ対応できます」
と返事をくれても、そこから家族間の意向の違いを擦り合わせて行っては間に合わないことがあります。
大事なシーンほど緊急性の高いことが多いです。
いざというときのためにも、”もしも”をしっかり練っておきましょう(‘ω’)
🌸まとめ
後輩には上記のように伝え納得してもらえました。
誰が“連携の軸”になるかが決まっていれば、みんなが安心して動ける。
それが結果として“責任の明確化”にもつながります。
それでも「うちの窓口は複数で!」と言われる方も中にはいらっしゃると思います。それはそれでもちろん構いませんが、どうしても一つ一つのアクションが遅れ、その遅れによって起こるご本人のリスクなども広い目で考えなければなりませんよね。
窓口を一つにすることは、ケアマネや事業所のためではなく、ご本人を守るための仕組み。
代表者の負担は確かに大きいですが、ケアマネは常に伴走者として一緒に考えます。
信頼関係のもとで、より良い支援を一緒に作っていきましょう🍀
★おまけ★
レストランや新幹線など、屋内は基本的に窓際が好きです(●´ω`●)