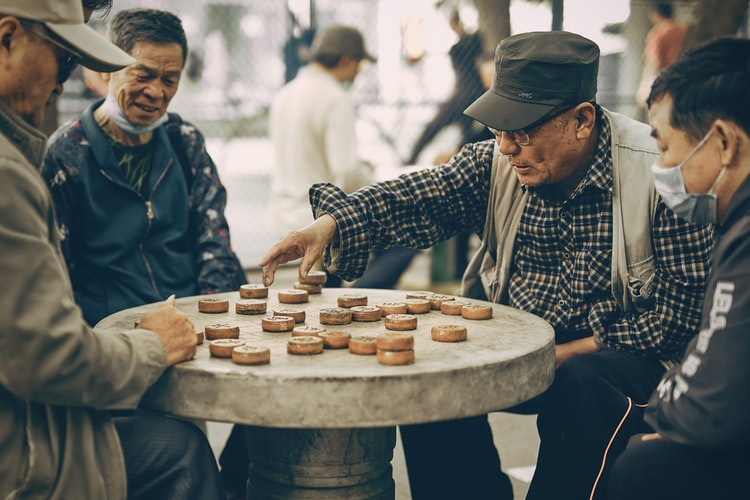こんにちは、まんぷくケアプランのまんぷくです(●´ω`●)
今日は、先日デイサービスの管理者さんから聞いた
“なるほど!”なお話をシェアしたいと思います。
テーマはずばり、「デイサービスの経営と要支援・要介護の違い」です。
※この記事は、ある通所介護事業所の実例をもとにしています。経営方針はそれぞれ異なりますので、あくまで一つの考え方として読んでいただけたら嬉しいです。
ケアマネは“経営”まで考えない
ケアマネの仕事は、ご利用者の希望や状態に合った事業所をつなぐことが中心です。
もちろん「数か月後に廃業予定」と聞けばその事業所の紹介はためらいますが、普段のケアマネジメントで事業所の収益構造まで踏み込むことはあまりありません。
ただ最近、「要介護の方が多い方が経営的に良いのでは?」という常識が、必ずしも正しいとは限らないことを知りました。
デイサービスが“要支援”を歓迎する理由
あるデイサービスの管理者さんがこんな話をしてくれました。
「うちは今、要支援の方を積極的に受け入れたいんです。」
正直びっくりしました。
「単価が低いのに、なぜ?」と尋ねると、こんな答えが返ってきました。
「要介護の方は入院や施設入所などで利用が途切れることが多いんです。
一方で、要支援の方は長く安定して利用してくださるので、結果的に稼働率が安定するんですよ。」
つまり、デイサービスにとって本当に大事なのは**“安定した稼働率”**。
空きが出ないことこそ、経営の肝なんですね。
要介護=高単価、とは限らない理由
要介護の方は「利用回数×単価」で収益が決まる仕組みですが、要支援は月定額制。
つまり、多少休まれても事業所の収益は変わりません。
一方、要介護の方が数回休むと、その分がダイレクトに減収になります。
単価が高くても「乱数(ばらつき)」が大きい、というわけです。
核家族化と“福祉の乱数”
今の時代、家族で看るのが難しくなり、施設入所も自然な選択肢になりました。
それ自体は悪いことではなく、「安全な環境で過ごす」という合理的な判断だと思います。
ただ、その結果として在宅での介護期間が短くなり、デイサービスの経営はより**乱数的(予測困難)**になってきています。
まとめ
この記事を読んで、「デイサービスに休むと迷惑がかかる」と感じる必要はありません。
福祉の経営はもともとアップダウンがある世界。
要支援には要支援の、要介護には要介護の経営バランスの取り方がある。
それはケアマネの知らない“裏の視点”ですが、知っておくとご利用者にも優しい選定ができるかもしれませんね🍀
★おまけ★
色んな業種の方と仲良くしていると色んな裏話が聞けて面白いです(●´ω`●)